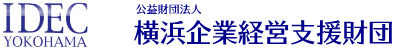
- タイトル
- 台湾アップデートセミナー第3回 台湾新製品から見る「地に足の着いた」IoT活用 (講義録)
- 本文
-
このレポートは、2022年1月にオンラインセミナーで講演した内容を文章にしたものです。
▶▶▶ 本セミナーの動画はこちら今回は台湾の展示会で見かけた台湾企業の新製品から見るIoTの活用法やビジネスへの活かし方を考えていきたいと思います。
今回のポイント
今回いくつかのポイントを先にお話ししたいと思います。以下を参考に新製品を見ていただくと技術にお詳しくない方でも参考になる部分があるかと思います。-
用語に振り回されるな!
5G、VR/AR/XR、エッジコンピューティング、AIなど・・・色々な用語が出てきますが、指していることが、技術なのか、技術によって実現したサービスなのか、既存の技術・製品の定義づけの見直しなのか、実はよくわからないまま話している人も多いように思います。こういった用語に振り回されず、その意味や実態をしっかり把握するようにしましょう。 -
実際に作っている製品を見よう!
例えばIoT、スマートファクトリー(工場) やDX(デジタルトランスフォーメーション)などは単なる概念にすぎません。そういったことを提唱している企業が実際に販売しているものはただのPCかもしれません。こちらも実態を把握するために大事なことです。 -
色々な技術や分野が融合しつつあることを知ろう!
5G、エッジコンピューティング、AI、センサーなど、最近のIT・IoT製品にはいろいろな技術が組み合わされています。よって一口に「IoT」と言っても販売しているものはセンサー部品かもしれませんし、小型のコンピューターかもしれませんし、5Gの通信モジュールかもしれません。もはや展示会でも明確に分類することが難しい製品が増えているのです。 -
ビジネスと技術の両輪を見よう!
技術だけでなく、それをどう使ってビジネスをするかを、垣根を越えて柔軟に考えることが重要です。もう理系も文系もありません。 -
製品ではなく、その製品が産み出された背景を見よう!
今回私がお話ししたいのは製品そのものの紹介より、その製品が産み出された背景です。台湾企業による「ちょっとだけオリジナル」を生み出す「考え方」を皆様の自社のビジネスに活かしていただければと考えております。
5G + Wi-Fi 6 (LIGHTSPEED)
5Gで屋外と、Wi-Fi 6で屋内と通信するモデム・無線ルーターです。同種のルーターは他からも出ていますが、この会社は社長が動画に出て一生懸命英語で解説しているのが好印象なので選びました。
なぜ英語で海外向けに発信しているかというと、台湾や日本のように既に光ファイバーが普及している場所よりも、そういうインフラが整っていない場所の方が可能性があるからだと考えたのだと思います。新しい機能は半導体・部品に実装される
先ほど、5Gで屋外と、Wi-Fi 6で屋内と通信する無線ルーターは似たようなものが他からも出ているとお話ししましたが、これは上記のような流れで半導体メーカーがそういった新機能が盛り込まれた半導体チップを売り込むことに起因すると考えられます。
世界有数のIT関係展示会であるComputex Taipeiでは新機能が盛り込まれた同じ半導体や部品を使った似たような製品が並びますが、そういった中でもアイデア賞を上げたくなるような面白い製品も出てきます。
いずれにせよ、量産が実現した部品に盛り込まれた新技術・新機能を使って新製品を出すスピードはすごく、ここは私たち日本企業も見習いたいところです。低遅延って重要?
先ほどの製品で出てきた無線通信規格5GやWi-Fi 6はどちらも低遅延を重視したものです。低遅延だと通信でのやり取りが速くなる効果があるのですが、それがなぜ注目されているのでしょう?
低遅延が重要だと考えられている分野で分かりやすいものは自動運転です。分かりやすく時速200kmで走る新幹線を想定し、前に障害があってブレーキをかけなくてはいけない状況になったとします。
この時ブレーキをかけるまでに1秒かかったらその間に55メートル、車両2両分くらい進んでしまいます。0.1秒でも5メートルです。実際はブレーキをかけてもすぐに止まるわけではありませんから、ブレーキをかけるまでの時間は短いほど良いわけです。
5Gでは数ms、つまり1000分の1秒単位の低遅延を実現していますが、自動運転においてはそのくらい厳密に通信でのやり取りの時間をコントロールすることに価値があるわけです。
他にも低遅延が求められる製品にはVR/AR(仮想現実)関連製品があります。例えば頭にヘッドマウントディスプレイ(HMD)をつけてVR/ARを経験する場合、頭を動かしてもHMDに表示される映像がすぐに切り替わらなければ、かなりの違和感を感じることになります。
正直、低遅延が求められる事例は今のところそこまで見えているわけではありません。しかし今から20年以上前に1Mbpsの40分の1から10分の1程度のスピードでしかネットが接続できなった時代には、現在のようなインターネットの発展が想像出来なかったのと同じく、現在の私達で低遅延が活かせる用途が見通すのは難しいように思います。5Gのインパクト
しかしながら数ms、1000分の1秒単位の低遅延が求められる事例が増えてくるのは技術的には大きなインパクトがあります。
今までインターネットの世界はベストエフォート(最大性能、最善努力)という考えが主流でした。ADSLや光ファイバーによる通信でも理論上の通信速度が達成されなくてもある程度割り切ることで成り立っている世界だったのです。特に遅延に関しては10ms、100ms単位での遅延など当たり前です。
しかし数ms、1000分の1秒単位で遅延を管理するとなると、通信がインターネットを経由すること自体ダメということになります。インターネットではなく、5Gのようなちゃんと遅延が管理されたネットワークを使うことになるでしょう。
そもそもネットワークを経由して遠くのクラウドやサーバーに問い合わせをするということを止め、クラウドやサーバーの機能をもっとユーザーの近くに置こうという考えも出てきます。この考え方を「エッジコンピューティング」と言います。
またクラウドやサーバー、そして通信機器自体の応答速度を早めるために処理能力を上げる必要があるかもしれません。そういう需要を見越して高速処理が可能な半導体チップなども出てきています。
またOSも応答速度の保証が可能な「リアルタイムOS」の重要性が増すかもしれません。元々リアルタイムOSとは工業や交通分野などで組み込み機器に使われていたものなのですが、5G時代に再度注目されるということがあるかもしれません。
こんな感じで5Gをきっかけに低遅延に注目が集まると、色々なところに変化が求められるということで、5Gは注目されていると言えると思います。よって5Gに関連する分野はたくさんあると言えるでしょう。エッジコンピューティング
先ほど「エッジコンピューティング」という言葉が出てきました。台湾の展示会でも良く出展される製品なのでもう少し詳しく見ていきましょう。
ネットワークを経由して遠くのクラウドやサーバーに問い合わせをするということを止め、クラウドやサーバーの機能をもっとユーザーの近くに置こうという考えなのですが、商品としては普通のPCやサーバーと大きく変わるわけではありません。
サーバーの設置場所としては、まず5Gのネットワークの中ではあるが、ユーザーにより近い基地局などに設置する場合があります。このメリットはサーバーの保守は通信会社などが行うので、ユーザーは保守の心配をしなくても良いというところです。
もう一つの設置場所としては自動車や工場やオフィスなどのユーザーと同じ場所です。この場合はネットワークを一切経由しないのでさらに遅延が短くなりますし、万一ネットワークにトラブルがあっても運用を継続できます。
ただこういったエッジコンピューティング用のPCはAIなどで求められる並列計算の機能を強化している以外は「工業用PC」と呼ばれるものとあまり違いはありません。実際工業用PCのメーカーがエッジコンピューティングを強調してマーケティングをしている場合も少なくありません。
そういう意味ではカタカナ言葉に踊らされず、製品を見ることが大事なわけです。スマートグラス
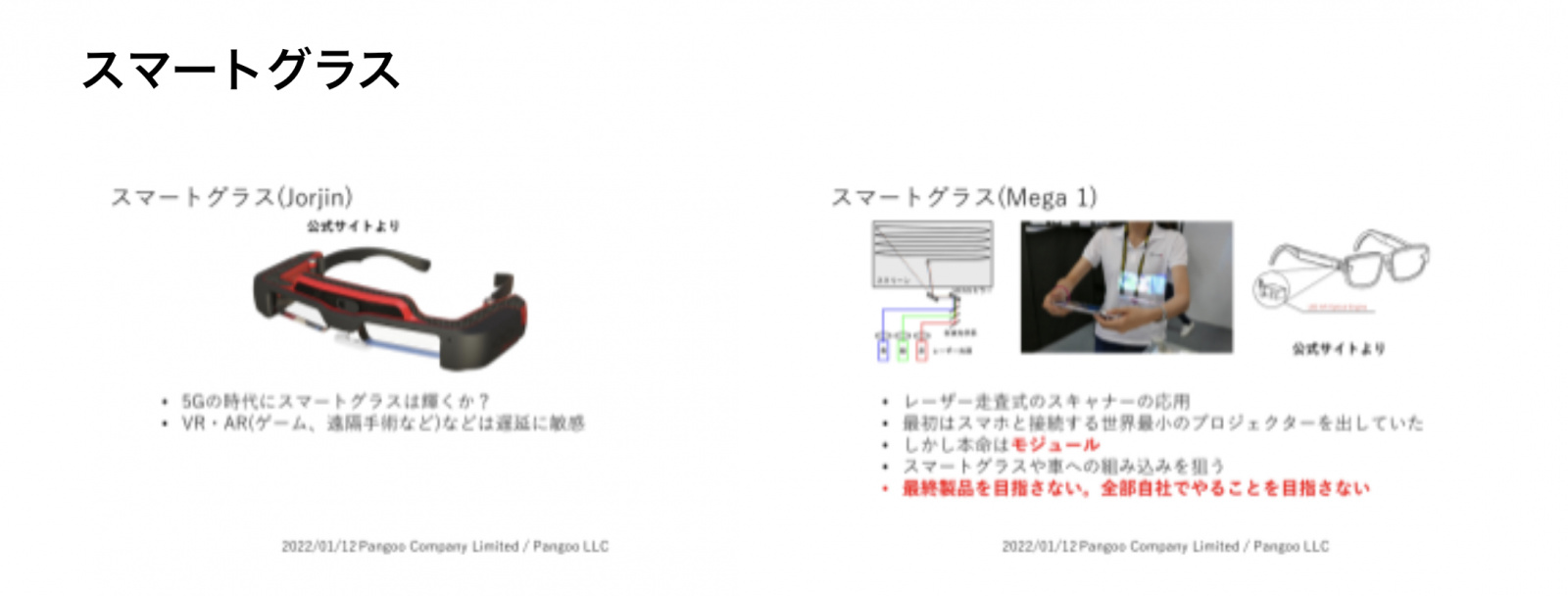
低遅延が求められる製品にはVR/AR(仮想現実)関連製品があるというお話をしましたが、関連分野としてはスマートグラスがあります。なかなか広がらない分野ですが、5Gを機に盛り上がってくるのかどうかは注目です。UWBによる屋内測位
無線通信規格で「UWB(Ultra Wide Band、超広帯域)」というものがあるのですが、副産物で、かなり精密な屋内測位が可能です。
原理としては、信号の到達時間をナノ秒=10億分の1秒単位に精密に計測することで距離を計算するのですが、誤差10cm程度で測位が可能です。また台数を増やすと高さを含めた3次元で計測が可能であり応用範囲も広がります。
高級車のキーレスエントリーでもUWBが使われていることがあります。車のキーレスエントリーは微弱電波で車と通信をしてドアを開錠したりします。
微弱電波なので通常は車の近くにいないとドアの開錠はできないのですが、車の持ち主が車から離れているときに、窃盗団が電波の中継器を使って、遠くの自動車にまでキーレスエントリーの電波を届けてしまい、キーが無くても開錠させてしまうことがあります。この手口を「リレーアタック」といいます。
UWBを使うと電波の到達時間を厳密に測定するので、例え中継器を挟んでも遠くにあるキーを判別し、「リレーアタック」を阻止することが可能です。屋内測位の活用方法
「リレーアタック」阻止以外にも屋内測位には以下のような使い道があります。- 屋内の案内・ナビゲーション
- 倉庫管理
- 工場内のリソースの管理(フォークリフトが棚の角など見えづらい場所に接近すると赤色灯点灯で警告、事故防止)
- 化学プラント内管理(平時の従業員の位置把握、危険時に携帯しているタグのボタンを押すとアラームと位置情報が送られる)
- 介護(平時患者がどこにいるかの把握、緊急時はタグのボタンを押すとアラームと位置情報が送られる)
GPSが届かない場所で精密な位置特定ができる屋内測位の活用はまだまだ創意工夫の余地があるように思います。IoTの基本の一つはセンサーによる情報収集
こちらは工場の設備に貼って振動や温度・湿度のデータを収集する「スマートタグ」です。フレキシブルな構造になっており、設備の表面が多少凸凹しても貼りやすいのがポイントです。
IoTの基本の一つはセンサーによる情報収集です。センサーで振動や温度データを収集することで故障の前に異常な振動が出るか、温度が上下しないかなどを確認し、機械の調子を予測したり、故障予知をしたりするのです。
こちらはステレオカメラモジュールです。2つレンズがあるので距離感もセンサーでつかむことができます。ヘッドマウントディスプレイ(HMD)や掃除ロボットなどに使われています。
こちらはミリ波レーダーと呼ばれるものです。天候に左右されにくく、数十メートルでも検出可能なので、自動運転の衝突防止センサーなどで注目されていますが、他にも部屋の中で人が倒れていないかなどの検出など介護分野への応用も進んでいます。カメラと違って、プライバシーを侵す可能性が低いのが良いところです。IoTとセンサーとAIの深い関係
IoTとAIは良く結びつけて語られることが多いですし、実際製品もそうです。
先ほどIoTの基本の一つはセンサーによる情報収集と言いましたが、このセンサーからのデータは膨大です。何せ1秒に1回データを記録すると1日で60×60×24=86400個のデータになるのです。
こういった形で集まった膨大なデータを「ビッグデータ」とも言いますが、これを分析するのは自動でないとなかなか厳しいです。こういった自動分析の一つとして現在はAI、もう少し細かく言うと「ディープラーニング(深層学習)」が注目されているわけです。
機械学習の高度化を進めた「ディープラーニング」により、色々なことができるようになり、現在何度目かのAIブームが起きています。「ディープラーニング」については詳細は省きますが、このディープラーニングはビッグデータを処理しなくてはいけないので、コンピューターの処理能力向上があって初めて可能となったものです。
AIというと人間の仕事が奪われるのではないかという報道がなされたりもしていますが、現在盛んに研究されているAIは人間と同等の知能を目指す話ではなく、あくまで特定の事項を機械学習により自動実行する「弱いAI」です。
こういったAIには先生役が必要です。よって何らかの形で人間が学習のノウハウや方法を教えないと効率よく動きません。またAIの活用方法も人間が考える必要があります。そういう意味ではAIの活用やそれによるビジネスは文系の方であっても創意工夫の余地があるのです。量産品の活用
この会社はオンライン教育の会社なのですが、以前は発展途上国向けに電卓のような簡易なデバイスを提供していましたが、現在は取り止めています。なぜなら大量生産の効果でタブレットPCやPCなどの価格が下がっており、発展途上国にも出回っているからです。
しかし安いデバイスはOSがMacやWindowsやAndroidではないかもしれません。そこでどんなデバイスでもインストールできそうなブラウザ上で全てのシステムを動かすようにしています。コロンブスの卵賞、イベント会場のフードデリバリー
球場やイベント会場の座席の背中にQRコードが貼られており、スマホでスキャンすることでブラウザが立ち上がり、座席番号を知らせなくてもネットで食事や飲み物の注文が可能です。決済はクレジットカードやQRコード決済などで行います。
単純に座席番号だけではいたずらで注文される可能性があるでしょうし、またおそらく席情報の入ったURLをQRコードに仕込むことで、専用アプリを入れなくてもブラウザだけで使えるという汎用性も上手いなと思います。
また球場や会場側は大がかりな設備導入が不要ですし、代金回収まで全て任せられるメリットがあるため、厨房やデリバリーに集中できます。
QRコード自体はデンソーが生産現場のために開発したもので広く公開されており、それを利用することは技術的に難しくないですが、活用方法が素晴らしいなと思いました。個人的にアイデア賞ものです。まとめ
もはやIoTは当たり前で、「IoT」と取り立てていう時代ではなくなってくると思います。また5G、Wi-Fi6、センサー、AI(ディープラーニング)など、VR/AR、エッジコンピューティングなどすべての要素は融合しつつあり、技術だけでなく、それをどうビジネスにつなげていくかが重要になってくると思います。
もちろん台湾企業だって全ての製品でヒットを飛ばしているわけではありませんが、その辺は製品を出すスピードで上手くカバーしている感じがあります。
本日の話は以上になります。「こういった場合はどうか?」など、個別の質問はこの場で私の感覚でお答えするのは不正確かもしれません。こういった個別の相談は是非IDEC横浜の各種相談制度をご利用ください。
横浜市内の中小企業であれば、台湾市場調査なども含めて一定の範囲までは無料で利用が可能です。是非海外進出に興味がある横浜の中小企業からのご相談をお待ちしております。
本セミナーの動画はyoutubeで公開中!! ▶▶▶ 動画
台湾サポートデスク
Pangoo Company Limited 代表 吉野 貴宣
この他の台湾アップデートセミナーのレポートもぜひご覧ください!
第4回 Food Taipei (台北国際食品展覧会)に見る日本企業のチャンス
-
用語に振り回されるな!
- 公開日時
- 2022年3月19日(土)