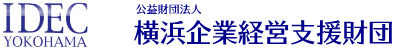
バイオデザインの現状
横浜医工連携推進コーディネーター
森尾 康二
2019年10月23日(水)
医工連携活動に関わっておられる方であれば「バイオデザイン」という言葉を最近よく耳にされるのではないでしょうか?「バイオデザイン」は米国スタンフォード大学で開発された医療技術開発の手法です。バイオという言葉からバイオテクノロジーを連想される方も居られるかもしれませんが、純粋に医療技術開発の為の手法です。
私が所属しています日本医工ものづくりコモンズ(通称:コモンズ)がバイオデザインの日本への導入のお手伝いをしたことから、現在もこの活動に関わっています。今回は日本でのバイオデザインの活動についてご報告したいと思っています。
日本でのバイオデザインの活動は2015年に始まりました。この活動には東京大学、大阪大学、東北大学の3大学が参加しています。各大学から毎年3-4名の、合計10名前後の学生及び社会人が参加して1年弱の期間この活動に専念します。参加者は大学ごとの3チームを作って、各チームごとに臨床現場の課題を抽出し、その解決策を提案し、最終的に1つの開発テーマに絞り込みます。
2015年にスタートして、第1期生、第2期生、第3期生、そして今年7月に第4期生が修了式を迎えました。この中で3つの開発プロジェクトがスタートアップとして巣立ってゆきました。
- *(株)リモハブ(大阪大学 谷口達典さん):遠隔心臓リハビリテーション
- *(株)アリバス(東京大学 田島知幸さん):難治性便秘の低侵襲治療
- * MAV(大阪大学 三隅祐輔さん):大動脈弁狭窄症の低侵襲治療
- (この3つのグループ以外にも起業を目指しているグループがいくつかあります)
こうしたスタートアップが目指すゴールは、その検討過程で正しく吟味されてきてはいるのですが、これを事業として成立させるためには更に十分な人材、知識、実行力が必要です。コモンズの中には医療機器・医療技術の開発に経験豊富な方々がいますので、メンターとして指導するだけではなく、スタートアップの方々と一緒になって活動を行っています。
臨床現場にある課題・アンメットニーズからスタートして開発に結び付けるというバイオデザインの手法は今日、広く知られる様になってきています。横浜医工連携活動においてもこうしたニーズ発の医療機器・医療技術開発の手法を取り入れる機会を作って行ければと思っています。
以上