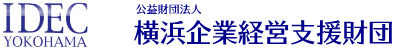
医療とAIについて
横浜医工連携推進コーディネーター
山越 淳
2019年9月25日(水)
近年のAI(Artificial Intelligence)の技術の進歩はめざましいものがあり、様々な分野でその活用が期待されています。医療分野も例外ではなく、インターネットで少し検索しただけでも、多くの記事がヒットします。
- ソフトバンクGが出資する製薬ベンチャー、AIと新薬で大日本住友製薬と提携
- AMEDにおける「先進的医療機器・システム等開発プロジェクト」に採択
AIによる皮膚がん診断支援システムの開発を加速 カシオ計算機株式会社 - キユーピー、AI×食でがん予防 サプリで体質改善
- 放射線治療をAIで効率化するベンチャーと京都大学病院の挑戦
- AIで冠動脈内腔を自動検出、GEヘルスケアなど
多くの企業や団体が、様々な医療分野にて様々なその活用を検討しており、一つの成長が見込まれる分野の一つであると考えられます。
なお、既にご存じの方も多いと思いますが、米国では、AIを用いた診断装置(軽度以上の糖尿病性網膜症を診断する装置)が、2018年に医療機器として承認されています。
- IDx:Press Release: FDA permits marketing of IDx-DR for automated detection of diabetic retinopathy in primary care April 12, 2018
- FDA NEWS RELEASE April 11, 2018
FDA permits marketing of artificial intelligence-based device to detect certain diabetes-related eye problems
日本では、以前、本コラムでも紹介したように、2014年11月25日に施行された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、医薬品医療機器等法)では、診断・治療等を目的とした単体プログラムは、“医療機器プログラム”として、他の医療機器(ハードウェア)と同様の規制が行われることになっています(医薬品医療機器等法 第2条第8項,第13号等)。このため、AIを用いた医療機器の他、そのようなプログラム自体も、法律上、医療機器に該当します。
このAIの医療分野への利用は、たとえば医療画像診断の分野では、近年、CT等による画像の量が大量となっていることから、医師による読影を補助するAIによって、読影の効率化と見落としの防止が期待されています。また、日々の診療から得られるデータを、いわゆるビッグデータとして取り扱うことで、そこから有用な情報を自動的に抽出する作業へのAI技術の活用も期待されています。また、今後は単なる診断だけではなく、治療技術に応用されることも予想されています。
一方、AI技術を診断や治療に用いたことによって、誤診断や医療事故が生じてしまった場合の責任の所在、あるいは、機械学習などの技術によって市販後も引き続き性能が変化するというAI特有の特性から生じる問題、更には、その様なプログラムやシステムの承認審査の進め方や規制の問題など様々な課題が指摘されています。
この様な課題を踏まえ、当局は、有識者による議論を進めており、いくつか報告書等が公開されています。
- 保健医療分野AI開発加速コンソーシアム
- 平成30年度次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業 人工知能分野 審査WG報告書
- AIを活用した医療診断システム・医療機器等に関する課題と提言 2017
この中で、「AIを活用した医療診断システム・医療機器等に関する課題と提言 2017」では、はじめに現在のAI技術の概要を整理した上で、「AI 医療システムのレギュラトリーサイエンス」として、診断支援・治療支援での具体的な利用形態を想定した上で、レギュラトリーサイエンスとしての見方を示すと共に、AI医療システムの倫理・責任についても議論がされています。
同報告書では、AI医療システムの特徴として、
- ① AI医療システムは学習により性能等が変化しうる。(製造承認を取得した時点の性能と、実際に使用された後の性能が大きく異なる可能性がある。)
- ② 深層学習などの方法によりAI医療システムはブラックボックスとしての性質を有する。
- ③ 将来、AIの支援レベルが高度化した場合、患者と医師等の関係性が従来と変わってくる可能性がある(将来の高度な自律能)。
などを挙げています。
同報告書では、その他にも様々な課題、議論等を紹介していますが、個人的には、究極的にAIが、医師等よりも高度な診断支援・治療支援の能力を獲得する可能性と、その様な状況となった場合に生じうる問題、例えば、「優秀な医師等以上の正答率であることが統計的に示されている診断支援AI医療システム(しかし一定の誤りがある)」が製品化された場合に、医師等がそのAIと異なる判断を選択することが、訴訟リスク等を考慮して可能なのか?(現実的には困難である。)といった課題に関心を持ちました。同報告書では、“その場合、医師等と機械の役割は実質的に変質することになるといえる。”とした上で、“その事態は、医師等の職業観、使命感、充足感にも影響する可能性がある。”とも指摘しています。
なお、このAIに関連して、平成30年12月19日に、厚生労働省から、下記通知が出されています。
医政医発1219第1号 「人工知能(AI)を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師法第17条の規定との関係について」
この通知では、平成29年度厚生労働行政推進調査事業費補助金により、「AI等のICTを用いた診療支援に関する研究」(研究代表者:横山和明東京大学医科 学研究所附属病院血液腫瘍内科助教)の研究結果を受けて出されたもので、“人工知能(AI)を用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合についても、診断、治療等を行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責任を負うこととなり、当該診療は医師法(昭和23年法 律第201 号)第17条の医業として行われるものであるので、十分ご留意をいただきたい。”としています。
AIの性能が、医師よりも劣っている段階では、医師がAIによる出力を確認し、誤りがあれば訂正することができるため、現実的に大きな問題は生じないと考えられます。また、そのようなレベルのAIであれば、必然的に、当該システムは、医師の支援をする役割に止まると考えられます。しかしながら、AIは、一人の医師ではとても取り扱うことのできない程の大量のデータを活用することができ、その大量のデータに基づいて学習を行います。また、一般に医療分野は、既に蓄積されているデータの多さと、出力すべきアウトプットの内容から、AIに向いた分野であると言われており、近年の深層学習等の技術の進歩を考えると、少なくとも特定の分野で、AIが医師等よりも高度な診断支援・治療支援の能力を獲得する可能性は十分にあるのではないかと考えられます。その際に、AIによる判断の結果の妥当性とリスクを、誰がどのように判断するのか。といった課題が、今後大きな問題となっていくのではないかと考えられます。そして、その様なAIの登場は、近年の技術進歩のスピードを考えると、決して遠くない未来なのではないかと思います。
以上本文中の情報については、最新かつ正確な情報を掲載するよう努めておりますが、その完全性・正確性・有用性について保証するものではありませんのでご了承ください。
本コラム内容に関連した具体的な医療機器開発相談は、一定の条件を満たす場合に限り個別対応が可能です。お問合せフォームからご相談ください。