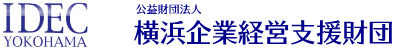
医療機器製造業経営者の事業承継(第3回)
横浜医工連携推進コーディネーター
真鍋 緑朗
2019年7月25日(木)
2017年からIDEC横浜の医工連携推進コーディネーターとして活動中の真鍋コーディネーターは、もともと横浜市内で電子部品製造会社を経営していました。そこで経験した、中小企業が医療機器開発に取り組む上での様々な困難について、シリーズでお送りします。
どん底からのスタート
私の入社当初は平屋建てだった工場も3階建てに増築、社名も(有)室町製作所からアールテック(株)に変更、下請け先の技術者グループもわが社に加わって業容は拡大していきました。しかし、それは増築や増員による借入金の増加という負担を背負い込んでいくことになりました。
不思議なのですがレントゲン屋として育ってきた技術屋の父が、このころから「X線だけやっていてもだめだ」という考えを持ち始め、多角化・異業種への参入に懸命となり、神奈川県知事賞を受賞したような成功事例もありましたが、その多くが失敗して技術系社員の何人かが退職していく事態となってしまいました。ここから会社を立て直すには力不足ながら私がやるしかないと決意し、父に代わり専務としてリーダーシップをとっていくことになりました。平成元年、30才の時で、まさにどん底からの実質的経営者としてのスタートでした。
笑われるかもしれませんが、まずは会社の雰囲気を変えようと、花を飾ったりBGMを流したりでした。当時の私にはそんなことから始めるしかありませんでしたが、幸い優秀な設計者が残っていたので、徐々に畑違いの事業を整理し、本業のX線装置開発に注力していきました。
ちょうどその頃、新型の移動型X線装置の開発依頼がありました。当時の装置は大きく重たくて扱いづらいものが多く、当社はインバータ式のコンパクトな機種を開発し、これがヒット商品となり、完成品メーカーとしての当社の名前が業界に知られる転機となりました。
その後さまざまな開発依頼が舞い込むようになり、毎年、新製品を生み出していき、なかでも動物用X線装置は大ヒットし、国内シェアの6~7割を占めるようになりました。医療用・動物用X線装置で当社の名前が知られるようになると、今度は非破壊検査などの工業用X線検査装置メーカーからも案件が持ち込まれるようになり売上も一気に増えて、医療用・動物用・工業用という事業の三本柱ができ上がっていきました。
この頃からISO9000にも取り組んでいたのですが、当時第一線を離れていた父が経営者のままではISOが要求するマネジメントシステムを構築しづらく感じていました。ちょうど私も40歳になっており、思い切って父に社長就任を打診したところ二つ返事でOKしてくれました。会長になってからの父は私のやり方に口を出すことはありませんでした。本当に感謝しております。父はその二年後に亡くなりました。
その後のリーマンショックでは工業用装置の受注が一時はほぼゼロになりましたが、医療用、動物用の受注と「ありとあらゆる工夫と努力」で危機をしのぎ、会社と社員を守り抜くことができました。ちょうどその頃から当社の主要顧客である中小医院や動物病院でも、X線撮影をフィルム現像するのではなくモニターに画像を映し出すデジタル化が進み始めていました。このデジタル化事業で「経営革新計画」の県知事認定をとり、「動物用デジタルラジオグラフィー」では日本で初めて農林水産省から動物用医療機器の承認を受けました。また、取引先の許諾をもらい、当社から海外に動物用X線装置の直接輸出を開始することもできました。
このように事業はどんどん拡大し、業界での地位も高まりましたが、その一方、薬事法は次第に厳しいものになっていき、対応に苦慮しておりました。法律が改正されるたびに、最大限の努力で対応してきましたが、あるとき県の薬務課担当者に「これは中小企業に医療機器から撤退しろと言っているのと同じですようねぇ」と聞くと「ある意味、そういう面もあります」との返事でした。実際、薬事法に対応できないいい加減な中小企業や医療機器は市場から消えていきました。平成17年の薬事法改正で製造販売業が新設された時のことです。
私はこのころから医療機器は中小企業が1社ですべてに対応していくのは厳しくなる、どこかと連携していかなければ生き残れないという思いが少しずつ出てきました。そしてこの連携のきっかけになったのがBCP(事業継続計画)への取組みでした。震災時に最短で事業を再開する時に、自社工場が復旧できないときの代替工場の確保が必要となります。医療機器の場合は許認可が必要なので、どの工場でもよいというわけにはいかず、同じ中小企業でしたが同業の医療機器製造業J社と災害時にお互いの工場を使用する覚書を交わしました。その提携によるお互いの交流はその後も進んでいき、そして平成28年3月、当社最大の取引先である東芝メディカルシステムズがキャノンの傘下に入ったことをきっかけに、会社の将来や事業承継のことを考え、父が創業し私が継いできた会社をJ社に引き継いでもらう決断をしました。そこに至る流れはとてもここに記すことはできませんが、おそらく亡き父もすべてを理解してくれていると思います。
会社を手放した私は、現在こうしてIDECの医工連携事業に関わらせていただいておりますが、これまでの経験を少しでも皆様に活かせたならと思っております。最後までお読みいただきましてありがとうございました。 (fin)