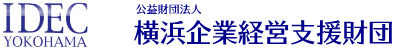
スマートリハ構想の御紹介
横浜医工連携プロジェクト アドバイザー
森尾 康二
2018年3月26日(月)
今回はリハビリテーション分野における国家プロジェクトである「スマートリハ構想」の現状について報告させて頂きます。本事業は2014年度に「未来医療を実現する先端医療機器・システムの研究開発(NEDO)」の中の「ニューロリハビリシステム」として発足し、事業が日本医療研究開発機構(AMED)に移った後も「スマートリハ構想」として、脳卒中により障害された運動や知覚の機能を回復する医療機器システムの開発を目指して続けられてきました。
本プロジェクトは統括責任者である慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室 教授 里宇 明元(りう めいげん)氏の下で産官学の共同事業として執り行われてきました。その成果として、スマートリハ室のプロトタイプが、昨年11月に医療法人社団健育会 湘南慶育病院(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの隣接地)内に開設され、先月24日に同所にて公開セミナーが開催されました。
里宇先生を初め関係するリハビリ医師、PT(理学療法士),OT(作業療法士)の講演もありましたが、殆どの時間を使い開発された機器の説明と実際の稼働が行われました。そのいくつかを御紹介します。
- 『脳波―BMI手指リハビリテーションシステム』
指を伸ばす感覚をイメージし、これによって発生した脳波を読み取って、指につけた電動装具を動かし、その運動感覚を脳へフィードバックする。 - 『自己運動錯覚誘導システム』
片麻痺患者の上肢について、健側の動作映像を麻痺側に反転再生し、麻痺側の手が動いている様に錯覚させ、脳活動を賦活する。 - 『近赤外線脳血流測定装置を用いたNIRSニューロリハシステム』
麻痺側の手の運動をイメージさせて、その脳活動をNIRSで計測して、患者にフィードバックする。
リハビリテーションの本質は失われた運動機能、知覚機能を回復することを目的として、殆どの場合自己による手足の運動と機械装置による他動的な運動の組み合わせで成り立っていて、こうした運動を継続することによって機能を回復させることを目指しています。今回のスマートリハ構想においては、更に加えて、運動や知覚を司る脳機能の賦活化と脳神経の活性化を計って、回復の範囲の拡大とスピード化を目指しています。まだまだトライアルのステージに在りますが、成果を出せる突破口を見付けられれば大きな福音をもたらしてくれるものと期待しています。